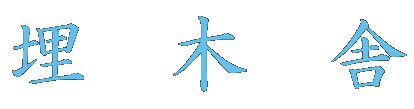「またか、宗盛」
清盛は、怒った。
おなじ嫡男でも、死んだ長子の重盛へは、こう我武者
には怒鳴どな れなかったものだが、宗盛だと、それが出る。
「わからぬやつよ。いくたび、ひとつ事を説と
きに参るぞ。今さら、またも、都を遷せなどという意見は、無駄なことだ。御辺ばかりでなく、公卿のまわし者や、山門の訴えにも、聞き飽いておる」
さほど、激語でないばあいも、このごろは、すぐ、入道のひたいには、青筋があらわれる。
心労のせいであろう。肉の落ちてきた顔には、まざと、ふかい皺しわ
がふえて見える。
「・・・・はい」
その人の子だ。宗盛には、分かりすぎている。
それだけに、彼は、しかられても、怒鳴られても、ふたたびの都遷うつ
しを ── 還都かんと の実行を
── 迫らずにはいられなかった。
「父君のお立場として、ひとたび、行われた遷都を、半年もたたぬまに、ふたたび、元へ還すなどということは、世上への御面目としても、お心にそまぬこととは」
「面目」
と、清盛は強くさえぎって、
「そこだ、御辺どもは、清盛が、小我しょうが
にこだわって、我が を張っていると、思うているのじゃろ。そうではない」
「いえ、その大きな御腹中は、宗盛にも、よく分かってはおりまする」
「ならば、もう、日ごとのように、意見がましい訴えを申しにここへ来るのはやめい」
「・・・・とも存じながら、なお、御意に逆らっても参りました仔細しさい
は、じつは昨夜、山門の明雲みょううん
座主ざす から、特に、お使いがございまして」
「明雲座主なら、清盛の心もよく知るお人、いつの御書状にも、ここへよこしておるのに、なんで、御辺の門へ、使いが行ったのか」
「さきの遷都に、ごうごうと、不平をならしおった一山の大衆を、今は、座主のお力を持ってしても、防ぎ難しとのお嘆きなので」
「そんなことは、今日の沙汰ではない。衆徒も公卿も、福原遷都には、初めから大不平だ。何を、今ごろあらためて」
「今ごろとは仰せられますが、昨今のそれは、ただ口先の不平ではなく、山門僉議せんぎ
の末、もし入道相国が、あくまで、福原の新都を固守するならば」
「固守したら、どうすると?」
「仲の悪い南都の大衆とも手を握り、近江、山城、河内の三国を、自己の力で治め、平安の地を復旧して、後白河法皇をお迎えせん
── と議を決したそうでございます」
「では、法皇を、奪い参らせんと謀はか
りおるのか」
「平安の都を復し、法皇を中心に、都づくりを催すとあれば、新都に安からぬ人びとは、風を望んで、帰るにちがいなく、また、近江源氏も、木曾源氏も、頼朝の鎌倉勢も、いちどに、上洛するであろうとの目企もくろ
みにござりましょう」
「ちっ、やっかいな衆徒めらが」
清盛は、舌を鳴らし、怖おそ
るべき彼らの知謀に、舌を巻いたのかも知れない。一瞬、蒼白そうはく
なふるえが、面おもて をかすめた。
「そればかりではございません」
「まだあるのか」
「堅田湖賊やら、近江源氏の山下義経と称する一党が、おいおいに、勢せい
を加え、これと山門、これと興福寺なども、隠密おんみつ
に結び合い、山門の僉議せんぎ
がなくも、必然、それらの暴徒が、旧都を占め、木曾や鎌倉勢を、呼び入れんことは、遠い日でもあるまいと、座主の御書状が、先を憂えておられました」
「・・・・・・」
清盛は、いよいよ、ひたいの筋を太らせて、黙然とあらぬ所をねめつけていた。
|