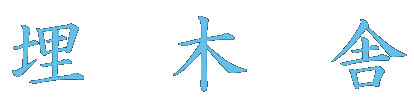六人の若僧は、みな高尾で、ともに、神護寺の再建
を計っていた文覚の弟子僧らしい。
彼らは、文覚の前に姿をそろえてぬかずいた。それに向かって、文覚があとの遺託やら訓戒をさずけると、彼らは、見得もなく若い涙を流してすすり泣いた。やがて悄然しょうぜん
と、師へ別れを告げて、立ち去って行った。
次に、文覚が眼でさし招いたのは、麻鳥あさどり
と蓬子よもぎこ
の夫婦であった。
この二人は、けさから群集の中に立ち交じり、一言でも文覚に別れを
── と思い続けて、やっと今、ここで望みがかなえられたのであったが、さて眼の前にさし向かうと、
「文覚さま・・・・」 と、ばかりで、涙ぐむほか、言葉もない。
「おう、やはりお前たちだったな」
文覚は二人の姿を見ただけで、十分、誠意を受け取った。そして 「どうだな、その後は。・・・・今も牛飼町にあのように暮しているのか。仲よくやっておるかの。もう赤ン坊も出来てよいころだが、子どもはないのか」
など、平常に変りもない話しぶりである。
「はい、子どもは一人生まれましたが、それは亡な
くして、後はまだございません。この蓬といい、わたくしといい、顧みれば、御僧とは長い御縁でございましたのに、こんなお別れを見ようとは」
麻鳥は、讃岐でみまかられた崇徳院の御非業ごひごう
も思い出されて、どうして自分の慕う人はみなこのような運命に見舞われるのかと、泣き悲しまれた。
「そうだ。思えば、おまえたち夫婦とは、まことに奇く
しき縁えにし
ではあった。・・・・保元の乱の直後、柳ノ水の焼け跡で、わしと麻鳥とが寝小屋を分けて暮していたとき、蓬子さんは、まだ常盤ときわ
どのの女童めわらべ
であったな。そして、よく柳ノ水へ、手桶ておけ
をさげて、もらい水に来ていたものだが・・・・。変ったのう、あんたも、世の人びとも」
「変るはずです。あれからもう十七年も経ちますもの」
蓬は答えながら、小さな包みを、文覚へ贈った。そして、こういい足した。
「ひと品は、薬です。配所で御病気にでも罹かか
られたとき、急のお凌しの
ぎになるようにと、良人が、七種ほどの薬をそれに入れておきました。もう一品は、けさ、わたくしが起きぬけにつくった蓬よもぎ
の餅もち
、船路のお慰みにでも、召し上がってくださいまし」
「蓬餅よもぎもち
とな。わしの好物を覚えていてくれたの。それと薬か。かたじけない」
文覚は、押しいただいて、
「時に、麻鳥。医学の方は」
と、たずねた。
「およろこびください。それもお耳に入れておきたいことの一つでした。師の和気百川わけのももかわ
様についてから、もう十年を越え、先ごろ、医学卒業の御印可を賜りました。施薬院せやくいん
の医生にならぬかと仰っしゃっていただきましたが、官に仕える心は持ちません。この先も、牛飼町の片隅に住み、貧者の友になりながら、おりには、柳ノ水のお掃除を守って、生涯、凡々と暮してゆきたいと願っております」
「うム、それはいい」
文覚は、祝福するようにうなずいて、
「おまえは、生涯凡々という。わしは性情の自然から、つい波瀾万丈はらんばんじょう
を通ってしまう。二人の歩みは、まったく別だが、わしが願うところも、おまええが志すところも、世を相愛の浄土としたいという念願では、一致している」
「そのゆに、何事もよくおわきまえなされながら
── また、人の世に絶えない相克そうこく
や戦いを、あのように憎んでおいでになる御僧が、どうして、仙洞せんとう
の御庭であんな乱暴をなされたり、人びとからは狂僧と呼ばれたりするのでしょう・・・・。それが、わたくしには分かりませぬ」
わしの言行と心とが、ひとつでないという不審か。年来、文覚自身も、その矛盾に思いをいたさぬわけではない。那智なち
の修業も、ひたぶるに仏道一念をつらぬいて菩薩身ぼさつしん
をうけんためではあった。だが精根しょうこん
、文覚の往生は、そこにないことを悟ったよ。わしには現実の世の物音に耳を塞ふさ
いでいることが出来ぬ。見まいとしても、世の醜さや悪政の裏面が見えて仕方がない。往生の素懐そかい
もそのために邪さまた
げられる。じっと、山林に行いしましていることの出来ない生命と知った。──
かかるうえは、生命の燃ゆるがまま、思うまま振る舞ってやろう。院政の積弊、また近ごろの平家の専横せんおう
ぶりをも、根こそぎ、揺すり脅おびや
かしてくれん。── そしてこの腐す
えた都のすがたも、否応なく革あらた
まるような何事かをわしは考えるようになった。その一新をもたらす大きな力が何かということは、今は言えぬ。・・・・が、今は言わぬが、麻鳥、ここ数年を見ておるがよい」
すぐ塚つか
の下には、たくさんな護送の兵が休んでいる。
また、仲綱の耳もある。
麻鳥はこれ以上、文覚がまた激越な語気に走ることを惧おそ
れた。
で、蓬よもぎ
に眼くばせして立ちかけたとき、ちょうどよく、下の仲綱も文覚へ向かって、出立を催促し出した。裸馬を塚の下へひかせ、早や立ち給え、と促すのだった。
文覚は、馬の背へ返って、
「さあひけい。麻鳥、蓬、おさらば」
と、振り向いていった。
塚のうしろに薄暗い木立があった。
そこに、やはり文覚のあとについて来た三十四、五歳の市人風いちびとふう
の男が、さっきからものも言わずに佇たたず
んでいる。
男は、文覚と別辞を交わす機会を、つい逸してしまったものか、また、さほどな有縁うえん
の者でもなかったのか、護送の列が動き出しても、彼は木蔭の位置から動かなかった。
「・・・・?」
だが、男の視線は、馬の背から振り向いた文覚の視線と、偶然ともなく、出合っていた。相互が、言外のものを、その眸ひとみ
に語っている。文覚は、すずやかな顔を前方へ向け直すと、四月半なか
ばの風光る中を、やがて、若葉がくれに、その影を遠くして行った。 |