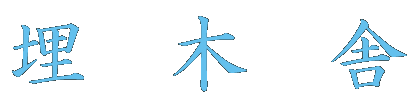堅物の廣瀬に変化が現れ始めたのはそのころからである。まずは髯をきれいさっぱり剃り落とした。三国干渉に憤って伸ばし、
「臥薪嘗胆の髯だ」 と言って、交際に障るという友人からの忠告を無視して、残していた髯だった。
ダンスの稽古にも通い始めた。最初の先生はロシア軍艦・アムール号の艦長、ドブロトボルスキーという中佐だった。彼は自宅で、それこそ汗水を垂らしながら教えてくれたが、廣瀬のこの方面の才能はひどかった。
「あなたはどうして、そんんい体を硬くするのか」
何度も言われ、力を抜こうとするが、うまくいかない。ダンスをしていることがどうにも面映く、そう思えば思うほど、軽やかに手足が動かなくなるのである。
どうにか格好がついたころ、二人で師匠につかないか、と誘ってきたのは陸軍の駐在武官、田中義一である。田中は当時、少佐で、後には総理大臣になる男である。
「よかろう。一人じゃどうも億劫だが、二人なら勇気が出る」
二人が弟子入りしたのはアレクサンドル劇場付のダンス教師だった。一足飛びにプロに弟子入りするというのは、なんとも無鉄砲な印象である。廣瀬の無鉄砲は、親友・財部彪の結婚話で山本権兵衛の自宅に談判に行った経歴で明らかだが、田中も当時から相当な傑物だったようだ。
教師の訓練は厳しかった。大きな鏡の前に立たせ、腰に両手を当てて腰の振り方を教える。手にはむちを持っていて、指示通りに出来なかったり形が悪いと、容赦なく尻を打たれた。
「何とかこう、手っ取り早く実地で使える踊り方をご指南願えませんかね」
たまりかねて田中が言うと、またこっぴどく叱責された。 |
| (舞踏も二三の手は覚えしが、とても臆面もなく令嬢たちと相伴いて飛び跳ねることが出来ず、毎度ながら控え居り候処、先方より口をかけられ、時としては義理一片に真似事致し、吾ながら可笑しいやら恥ずかしいやら) |
|
| よほど親しい相手となら踊れるようになった近況を、廣瀬はこう書いている。 |
| (仮に武夫が縁ありて碧眼金髪の児を御紹介申す期有之候えば、御義絶などと御憤慨遊ばされまじきや、その点につき先ず第一にお伺い申し上げたく候。実は武夫も当露国において、などと切り出し候わば、御吃驚の御程度はいかがなものにや) |
|
廣瀬が日本の兄嫁、春江にそう書き送ったのは明治三十四年の春ごろである。コワレスキー家と知り合って一年八ヶ月、アリアズナが廣瀬に好意を持ってから一年三ヶ月近くが経っていた。
廣瀬に妻帯する気持が芽生えたことを察した春江は、西洋館を借りておくから、いつでも西洋人の奥さんを連れて帰るよう返信した。それだけでなく実際、東京・牛込の洋館のある家に引っ越した。春江は廣瀬の戦死後、その西洋館を固く守り、子供や孫たちが入ることも許さなかったという。
しかし、廣瀬は春江の返信に対して、はぐらかすような手紙で答えている。 |
| (そんなことなら、ロシアから、立派な、素敵な奴を、亭主を尻へ敷島の国へ連れて立ち帰り見ん。そやつがわざと群衆の前にて亭主に靴紐を結ばせなどしても、決して陰口を下したもうことなきを望むことに有之候。呵々) |
|
| このころの廣瀬はすでに、ロシアと日本の開戦が避けられないことを感じ取りつつあったと言われる。もしもアリアズナを妻にして帰国後に開戦となった場合、妻はどんな扱いを受けるか、また、海軍士官としての自分がどんな処遇を受け、対応ができるか。そんなことを考えれば考えるほど、廣瀬としては本心を隠す以外に道はなかったかもしれない。個人より家、そして国家を大事に思うのが当然の時代であり、その時代の軍人として廣瀬は生きていたのである。 |