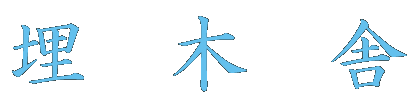この章の最後は、廣瀬の家族たちのその後の触れたい。妻子を持たなかった廣瀬にとって、家族と呼べるのは長兄、勝比呂の一家である。勝比呂と妻、春江の間には一人娘の馨子だけで、男児はいない。
廣瀬は、馨子を我が子のように可愛がり、春江には実際の姉のように甘えた。父の重武らが亡くなった後、廣瀬が書いた私信の多くは、この二人に宛てたものである。
廣瀬より一歳年下の兄嫁、春江は後に、婿養子の末人や娘たちから、西太后とあだ名されるほどのしっかり者だった。
日露戦争後、戦艦・富士などの艦長を務めた勝比呂は大正九年、五十九歳で病没した。温厚でかつ周到な人で、死に際しては春江に宛てた入念な遺書を残した。これまでの献身と内助の功を称え、春江の実家への感謝まで記した上で、廣瀬の祭祀と、廣瀬の知人や敬慕者への交誼に十分心を尽くすよう、懇ろに頼んだ。
春江はその遺言を完璧に守った。廣瀬の命日の三月二十七日には、自宅の二階八畳の間を
「神様に部屋」 として、勝比呂と廣瀬の木主を安置し、神道儀礼による祭祀を行った。床の間には遺影や遺品、勲章を飾るなどして廣瀬を偲ぶ人たちを迎えた。この部屋には、旅順口閉塞作戦に参加した生き残った人たちが欠かさずおまいりに来た。
命日には毎年、万世端にある廣瀬の銅像の洗浄式が行われたが、春江は男児の孫を連れて必ず出席した。中佐の跡継ぎは男児でなければならず、しの男児はその男児は式を行ってくれる人たちに謝意を示さねばならない。春江はそう思っていたらしい。
孫たちへのしつけ、教育も厳しかった。婿養子の末人も海軍士官だったため、こんな説教が常だった。
「お前様方のお父様は、ご自分でお金儲けなさるのではありません。お上が、国民から税金として集めた中から分けて頂くのですから、決して無駄遣いしてはなりません」
食事はいわゆる一汁一菜。夕食では時折、肉か魚が一皿ついた。そいう暮らしぶりだった。
「服はお下がりばかりでねえ。うちはきっと貧乏なんだと、ずっと思っていました」
末人と馨子の次女、高城知子はそう書き残している。
春江と馨子が病没した後、廣瀬の祭祀を守ったのは末人だと言っていい。海軍中将で終戦を迎えた後、伊豆で隠遁生活を送っていたが、昭和三十年代の終わり、廣瀬神社
(竹田市) の改修奉賛会の理事長に推された。そして募金に駆け回ったのが縁で、二代目の宮司になったのである。資格を得るために、国学院で老学生も経験した。
宮司を務めたのは七十九歳で病没するまでの約三年間だった。この間に渇水に悩んだ農家の人たちが、雨乞い神事を頼みに来たことがある。
まだ神職になって日が浅いから祝詞を作る時間が欲しい。そう言って一旦、彼らを帰した末人は後日、雨乞いの祭文ができたからと言って彼らを呼び、雨乞い祭を行った。その最中に雨が降り始め、霊験あらたかだと評判になった。
実は、何のことはない。艦上勤務が長かった末人は、雲や風の流れを見て、雨を予測できた。この日なら間違いなし。そう読んだ日に神事を行ったのである。
この逸話には、どこかいたずら小僧めいた稚気がある。三十五歳と十ヶ月で死んだ廣瀬は、子供こそ残さなかったものの、その精神や心は家族や知人、あるいは日本人すべての中に残っているのではないか。そんな気がしてならない。 |