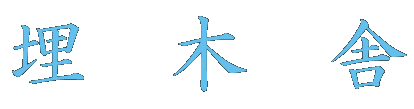| かくいふほどに、七月になりぬ。七日、すきごとどもする人のもとより、たなばたひこぼしといふことどもあまたあれど、目も立たず。かかる折に、宮の過ごさずのたまはせしものを、げにおぼしめし忘れにかるかなと思ふほどにぞ、御文ある。見れば、ただかくぞ、 |
| 宮
『思ひきや 七夕つ女 に 身をなして 天あま
の河原かはら を ながむべしとは』 |
|
| とあり。さはいえど、過ごしたまはざめるはと思ふとも、をかしうて、 |
| 女
『ながむらむ 空をだに見ず 七夕に 忌まるばかりの わが身と思へば』 |
|
| とあるを御覧じても、なほ思ひはまつまじうおぼす。 |
こうしているうちに、七月になった。七日、好色の道が好きな男たちの所から、織女とか彦星とかいうことなどを詠んだ恋歌が多く来たけれど、目にも入らない。
こうした折に、宮が時機を逃さず歌を送ってくださったものなのに、本当に私のことをお忘れになってしまったのだと思っているその時に、御文があった。見ると、ただつぎのように一首だけ、 | | 『今まで考えてみたこともありましょうか。織女星にわが身をなぞらえて、天の河原を物思いにふけってながめるようになろうとは。年に一度の逢瀬もかなわぬ身です』 |
| | と書いてある。そんなお歌でもやはり七夕のときを見過ごしなさらなかったと思うにつけても、うれしくて、 | | 『宮様が眺めていらっしゃるという空さえ見る気になれません。年に一度の七夕に宮様からきらわれるほどのわが身と考えますと、悲しくて』 |
| | と書いたのを宮がご覧になるにつけ、女を思い切ることはとても出来ないと思われる。 |
|
| 晦日つごもり
がたに、 宮 「いとおぼつかなくなりにけるを、などかときどきは。人かずにおぼさぬなめり」 とあれば、女、 |
| 『寝覚めねば
聞かぬなるらむ 荻風をぎかぜ
は 吹かざらめやは 秋の夜な夜な』 |
|
| と聞こえたれば、立ち返り、宮
「あが君や、寝ざめとか。 『もの思ふ時は』 とぞ。おろかに。 |
| 宮
『荻風は 吹かばいも寝で 今よりぞ おどろかすかと 聞くべかりける』 |
|
かくて二日ばかりありて、夕暮に、にはかに御車を引き入れて、下がりさせたまへば、まだ見えたてまつらねば、いとはづかしう思へどせむかたなく。なにとなきことなどのたまはせて、帰らせやまひぬ。
そののち日ごろになるぬるに、いとおぼつかなきまでも音もしたまはねば、 |
| 女
『くれぐれと 秋の日ごろの ふるままに 思ひ知られぬ あやしかりしも』 |
|
| むべ人は」 と聞こえたり。
宮 「このほどにおぼつかなくなりにけり。されど、 |
| 宮
『人はいさ われは忘れず ほどふれど 秋の夕暮 ありしあふこと』 |
|
| とあり。あはれにはかなく、頼むべくもなきかやうのはかなしごとに、世の中をなぐさめてあるも、うち思へばあさましう。 |
| 月末のころに、宮から
「ひどく疎遠になってしまいましたが、どうして時々でもお便りを下さらないのですか。私など人並みの数に入れておられないのでしょう」 と言って来られたので、女は | | 『物思いの寝覚めをなさらないからお聞きにならないでしょう。君をお招きする荻風は秋の夜ごと吹かないことがありましょうか』 |
| | と申し上げると、すぐに、
「あが君よ、寝覚めと言われるのですか。『物思ふ時』 は寝るどころではないと申しますよ。いい加減なお心ですね。 | | 『私を招く荻風が本当に吹くのなら眠らないで、いま吹くかいま目を覚ませるかと聞けばよかった』 |
| こうして二日ほどたって、夕暮れに、突然宮がお車を引き入れて下り立ちなさったので、まだ夕暮れの明るい所でお目にかかったことがないから、ひどくきまりわるく思ったけれど、どうしようもなかった。宮は何ということのないお話をなさって、お帰りになった。
その後、何日かたったのに、ひどく待ち遠しい気持ちになるまで何とも言っておいでにならないので、 | | 『滅入った気持で夕暮れをむかえ、秋の何日かが過ぎるにつれて、よくわかってきました。この間の夕暮れに宮様がお見えになったのは、へんでしたですよ』 |
| | まったく人間というものは」
と申し上げた。宮からは 「この何日かの間、ごぶさたしてしまいました。けれども、 | | 『あなたの方こそあやしいものですが、私は時は過ぎても忘れはしませんよ。秋の夕暮れにこの間お逢いした時のことを』 |
| | と詠んでこられた。まことにとりとめもなく、頼みになるはずもないこのゆなかりそめの和歌によって、私の人生を慰めて暮らしているというのも、考えてみれば情けなくなってこることだ。 |
|