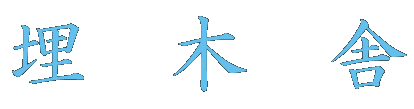| お夏、夜毎
にこの所へ来りて弔とむら ひける。そのうちに、まざまざと昔の姿を見し事うたがひなし。それより日を重かさ
ね、百ヶ日にあたる時、塚の露草つゆくさ
に座して、守り脇指わきざし を抜きしを、やうやう引きとどめて、
「ただ今むなしうなり給ひてやうなし。まことならば、髪をおろさせ給ひ、末々すゑずゑ
なき人をとひ給ふこそ、菩提ぼだい
の道なれ。我々も出家の望み」 といへば、お夏、心をしづめ、皆々が心底しんてい
さつして、 「ともかくも。いづれもが指図はもれじ」 と、正覚寺しやうかくじ
に入りて、上人しやうにん を頼み、十六の夏衣、今日けふ
より墨染すみぞめ にして、朝あした
に谷の下水したみづ をむすびあげ、夕ゆふべ
に峰の花を手折たを り、夏中げちゆう
は毎夜、手灯しゆとう かかげて、大経だいきやう
の勤めおこたらず、有難ありがた
き比丘尼びくに とはなりぬ。 |
お夏は毎夜ここに来て、清十郎の供養をしたが、ありし日の恋人の姿をまざまざと目前に見ることもあったに違いない。月日が経過して清十郎の百ヶ日になったとき、お夏が塚のそばの露草に座し、自害しようと懐剣を抜いた。付添いの女たちがようやく引き止めて、
「今自殺したからといって、何の役に立ちますか。それほどの真心をもって髪をおろして出家し、末長く供養にはげむことこそ、亡き人の極楽往生の為になりましょう。われわれもお供して出家したいと存じます」
と説いた。
ともに出家しようという女たちの気持が通じて、お夏は心をしずめ、 「なにはともあれみなみなの指図にはそむくまい」 と腹をくくり、姫路にある正覚寺の上人に頼み込んでらくしゅ落飾した。そして十六歳の夏衣を墨染めの衣にかえ、朝には谷の水をくみ上げ、夕べには峯の花を手折り、参籠修行には手灯をかかげる難苦にたえて、読経の勤めもおこたらず、ついには尊い比丘尼となった。
|
|
| これを見る人、殊勝しゆしよう
さ増して、 「伝へ聞く中将姫ちゆうじやうひめ
の再来なるべし」 と、この庵室あんしつ
に、但馬たじま 屋も発心ほつしん
起りて、右の金子きんす 、仏事ぶつじ
供養くよう をして、清十郎を弔とむら
ひけるとや。その頃は上方かみがた
の狂言になし、遠国ゑんごく 村々里々まで、ふたりが名を流しける。これぞ恋の新川しんがは
、舟をつくりて、思ひを乗せて、泡うたかた
のあはれなる世や。 |
事情を知った人がいたく感じ入り、
「伝え聞く中将姫の出家が十六歳だったというから、お夏はその生まれ変わりであろう」 と評したが、このような経過はさすがに但馬屋をゆり動かして菩提心をおこさしめ、例の七百両の金子は結局清十郎の仏事供養のために使われたという。
お夏清十郎のこの事件は、間もなく上方で芝居に組んで興行してまわったので、二人の名は遠国の村や里にまで流れ広まった。これこそは、恋の新川につきせぬ男女の思いがこもる舟をおし出してみたものの、しょせんは大海のうたかたとなって消えゆくに似た、あわれな物語である。 | | 『現代訳
西鶴名作選』 訳者:福島忠利 発行所:古川書房 ヨ リ |
|