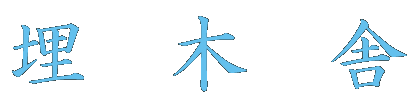「法皇の御通夜に侍しながら、コソコソ、悪謀をささやき合い、悲しみにぬれながら、眼は互いに、人の肚
ばかり猜疑 し合っている。
── 千僧の読経、金堂の荘厳も、ウソの幻覚化に役立っているだけのものだ。あんな、空涙の海みたいな中に、長くいたたまれたものではない」
悪左府頼長は、肚の中で、昂然
と、つぶやいた。
(── やむなきことが起こって、急に、宇治へ参らねばならぬので)
と、安楽寿院における御
柩 の宿直
を、二日目に中座して出て来たときの ── かれが牛車
うちでの ── 捨て言葉であった。
かれの車は、夜のやみになぎれて、すぐ近くの、田中殿の門へかくれた。
そして、ひそかに、新院に拝謁
し、
「御父子の、お別れすら、許されぬなどとく例は、和漢の朝を通じてもないことです。どんなに、御無念であったでしょう。── いまや内裏は、新帝を擁し奉って、女院や佞臣
らの巣窟 と化し去りました。人皇数十代の御世を通じ、いま程、朝廷を外道
の跳梁 にまかせた時代はありますまい」
と、眼
じりをあげて言った。
さなきだに、新院は、炎のような御無念を、御簾に秘
して、なお、悶々たる御 気色
の夜であった。 ── 父法皇のみまかり給う急に駆
けつけながら、惟方
の毒舌や、武者の暴力に阻まれて、父君との死目にもお会いになれず、惨たるお姿を乗せて、むなしく車を回した日の口惜しさは ── 無念さは ── いかに御自身、なだめようにも、なだめきれない御
容子 である。
いま。
── 頼長の一言が、お耳を打つと、新院は、きっと、何かに憑
かれたようなおん眼にになって、
「左府、差府。・・・・公ひとりが、朕
の恃 みぞ」
と、落涙された。そして心中のものを、一気に吐くかのような語気で、仰っしゃった。
「むかしを、今に思うても、天智、仁明
、花山、三条などの諸帝とて、みな、その質をもって、帝位に挙
げられ、順をこえて、祚 を践
まれている。時の母后の愛情や、奸臣の意志などで、左右されるべきものではない。── 朕は、身に徳はないが、正しく、先皇鳥羽の太子に生まれ、ひとたびは帝位を辱
うし、上皇の尊号に列 なる者。・・・・去年、近衛帝の崩御のあとは、当然、朕の一ノ宮こそ、太子たるべきはずであった。──
それを、文にもあらぬ、武にもあらぬ、四ノ宮 (後白河) に超
えられて、父子ともに、生きつつ世から葬らるることの無念さよ。・・・・それも、鳥羽のお在
しますうちは、ぜひもなけれ、すでに登遐
をみた後は、わが身が、ふたたび帝位に即くも、世人の心に背くことはあるまいと思うが。・・・・公は、どう思うか」
── 頼長は、瞑目
した。
深刻な面
をして、深思するばかりであった。
しかし、それへのお答えは、とうに、かれの胸には、用意されてあるはずだ。。世事の機微も、人間の心の底深い泥溝
なども、のぞいたことのない相手のお人である。その上皇崇徳をして、ついに、こういわせたのは、頼長なのだ。ことばは、新院のお口から出たが、頼長の野望を、頼長に代わって、仰せ出されたようなものである。
「──
時でしょう」 と、頼長は、浩嘆
して、やがて言った。
「陛下が、そう御決心あそばし給うこそ、天の時が来ているものと思われます。天の与うるを取らざれば、かえって禍
いを受くという。再即位の例は、斉明
、称徳 の二朝にも、先例のあること、御憂慮には及びません」
頼長は、才略に、自負満々であった。
軍事についても。かれは、六韜
や三略をそらんじているし、実兵力には、源氏の棟梁
。源ノ為義一族を、握っているという、自信もある。
こうして、新院を擁し奉った頼長の謀略は、この夜から、また翌一日にわたって、密議されたのであった。かねて、頼長から誘われていた下心ある公卿たちも、安楽寿院の方を抜けて、夜中や未明に、ここへ移って来た。牛車や輿
は、すべて奥深く隠し、門には、見張りを立たせ、放免を使って、情報を集めるなど、すでに前衛戦に入ったかたちである。
しかし、ここでは、諸国の軍兵を糾合
するにも、ほかの手配にも、不便なので、頼長は一たん、宇治へ去った。 |