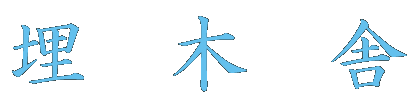だれが企
むともなく、また、決意したのでもなく、美福門院をかこむ集合は、そのまま、極めて自然に、軍議のかたちになってしまった。
法皇は、御自身の没後、兵乱は必然と考えておられたものか、崩ずるに先だって、万一の時には、源平の将士十人を召し、後白河天皇を守護し、美福門院に禍
いあらしむるなと、十将の名を書き遺しておかれたのである。
それによると、源氏の義朝、義康、頼政を筆頭に、平氏では信兼、維繁、助経などの名が見える。しかし、当然、あるべきで、落ちている者が一人あった。
「なぜ、安芸守清盛の名が、これにもれておるのでしょうか?」
信西は、腑
に落ちない顔をした。そして、女院の御返事に、それを求めるような、眼をむけた。
「清盛の父忠盛は、以前、新院の一ノ宮 (重仁親王)
へ、よく伺候していたことがあります。いまの忠盛の後家、清盛の義理の母は、もと一ノ宮の乳人
であった有子という婦人でしょう。亡き法皇さまは、そのような細かいことも、お忘れなく、いつまでも、お心の奥に持っておられるお性
でした」
美福門院は、そう説明されたが、かねて清盛のことについては、信西の妻の紀伊ノ局から、ないないの推薦を受けておられたらしく、すぐ次のように、言い足した。
「まこと、法皇さまが、これをお書き遊ばすときは、わたくしはお側におりましたし、また前もって、御相談にもあずかりました。故院のお旨としては、清盛は平氏の大族
でもあり、頼もしい者なれど、義母の有子は、一ノ宮へ心を寄せまいものではないゆえ、わざと、省
いておく。しかし、清盛に二心だになくば、召し呼ぶもよい。ことある時の計らいにせよと、仰せ遊ばしたのを、いま、思い起こされ魔スル」
信西は、女院のお言葉を、うけとって、結論をつけた。
「清盛に、二心は見えません。祗園の神輿事件から、左府からは、ひどくきらわれて、一時、故院
の御寵遇 も薄らいだのは事実ですが、それはみな、他人の讒
によることです。いま、大事を前にして、清盛ほどな将を、強いて、除外するなどは、もってのほかな不利でしょう。 ── 一座の君 (忠通をさす)
には、どうお考えになられますか」
「もとより、自分は初めから、安芸守を、除外もせぬし、きらってもおらぬ」
「では、加えますか。清盛も」
「よろしいでしょう」
十将の名に、さらに一名を加え、ここに、綸旨
をうけて内裏 方に召される武将は、十一名と決定した。
もとより、十一名は、それぞれ多くの家人郎党をかかえている一族の長
である。従って、地方の領国の武士だの、支族や縁類の徒は、すべてその十一代表の手から召集させ、朝廷直接には、令を出さない。
翌々七日目 ── すなわち七月八日には、もう、召された軍兵が、続々と、安楽寿院の仮御所に、つき、外門
内門に、あふれかえった。
到着状を見ると、まず、下野守源ノ義朝、陸奥新判官義康、周防判官李実などを始め、平ノ維繁、新藤助経、平判官実俊などの名が見えた。おのおの、手勢、家の子を引き連れ、旗場
分 けして、おたがい、気の荒い武者同士の、仲間争いを、まず戒めあった。
その中に、郎党を二百騎ほど連れて、人びとよりやや遅く、ここに着いた若い大将がある。記録所の筆生にむかって、到着の名のりをするのを聞けば、
「これは、安芸守清盛の二男、安芸
判官 基盛
と申し、生年十七歳です。 ── 父清盛は、かたじけなき綸旨を奉じて、自領の武士どもや、旧縁ある国々の者どもへも、檄
を送って、大勢をとりまとめ、なお後より参陣いたしますなれど、とりあえず、わたくしのみ急ぎ、馳
せ参じました」
と、いかにも、涼やかな、また、初々
しい言い方であった。
姿を見るに、藍と白地を黄に返した鎧
を着、黒羽の矢を負い、漆の弓を持ち、折り烏帽子
に、兜 はかぶらず、背にかけていた。
「・・・・おお、あの清盛が子にも、もうこんなよい息子があったのか」
と、人びとはみな、基盛に見とれた。その父、また、その祖父忠盛の面影までが、たれにも思い出されていた。同時に、とかく、迂闊
にすぎている自分自身の歳月にも、振り返らずにいられなかった。 |